今日も1日お疲れさまです。
2025年の夏の参議院選挙の焦点の一つに「消費税減税」があります。
普段の買い物でかかる消費税、その税率が下がるのであれば是が非でも下げてもらいたいものです。
そんな中ニュースで目にしたのは
「減税したらお店の人が値札の交換対応で大変」
という旨の内容があり、ただただ呆れるばかりでした。
そういった店舗もあるかもしれませんが、「いつの時代??」と思わず声が出たくらいです。
実際に消費税が増税された時、私は店舗勤務でいろいろ大変でした。
しかし今回は増税ではなく減税と状況が大きく異なります。
この記事では、消費税が増税になった時に起きた店舗での出来事と、今回の場合との相違点を「お店の人」の観点で説明します。
※ただし、私自身が勤務していた店舗の話なので、他の業種と共通するものではないものもあります。ご了承ください。
実際に消費税変更(増税)の際に行われたのは大きく分けて3つです。
- 商品の通常売価の変更(本体価格と税込価格の表記)
- 生鮮食品に貼られるラベルの表示の変更
- 変更当日のレジでの売価チェック
商品の通常売価の変更(本体価格と税込価格の表記)
私の勤めていた店舗では、増税になるまでは本体価格と税込価格の区別がなく、全て税込で一括表記でした。
これは小売業に限らず、どこの店舗でも同じような状態だったと思います。

それが消費税率変更で大きく変わり、「本体価格○○円・税込価格△△円」という表記になりました。

これに伴って全商品のPOP(商品名や価格の書かれたショーカード)の記載が全て変更になり、売場の全ての商品の表記がこの本体価格と税込価格の表記に変わったのです。
チラシも全てこの表記に変更になりました。増税なので税込価格で見ると実質的な値上げです。
当初は「これに便乗して多く儲けようとしてるんじゃ・・・?」なんて声も多数ありました。
生鮮食品に貼られるラベルの表示の変更
変更になるのは肉や魚、お惣菜のパックに貼られるラベルも同様です。
こちらも上記と同じで今まで税込売価で一括表記だったので、本体価格と税込価格の表記に変更されました。
これはそれぞれの部門に設置されているラベル発行機のメンテナンスが必要で、1日の商品の製造が終わった後に業者の方が行いました。

メンテナンス後に実際にレジを通してその通りになって初めて完了という流れです。
変更当日のレジでの売価チェック
上記2つの準備をして、当日です。
レジでも売価登録が表示価格の通りに行われるかどうかのテスト運用が行われます。
商品をカゴに入れていざ会計の時にトラブルになると今までの準備が全て台無しです。

消費税率変更当日は開店前に商品を揃えるよりも、「実際にレジを通して商品の売価が合っているかどうか」に重点が置かれました。
たしか専務か本部長クラスの人が「開店時の売場は揃ってなくてもいいから、売価チェックを優先」という通達がきたくらいです。
相違点
増税ではなく減税ということは、値上げではなく実質値下げになります。
前提条件として、商品の売価設定や生鮮食品に貼られるラベルの売価(100g当たり〇円など)が間違ってないものとして考えると、増税時よりも精神的な労力は大きく減ります。
その理由は、実際のレジで通した売価が値下げになるからです。

消費税率の変更時などの大掛かりな売価変更の時、チェーン経営のスーパーの場合は本部で一括で売価変更をするのが大半で、店舗で商品を持ってきてわざわざ一つずつ売価変更なんてことはしないはずです。
売価チェックは「変更した売価が本当にあってるか確認してね」という意味合いで行われます。通常業務でも広告商品などの売価確認で行われます。
仮に店側が減税前のPOPの取り換えを忘れ、高い売価のPOPのままで販売していたとしても、レジで通る売価はそれよりも安い売価になるはずです。
「税込み220円(と表記)の物をレジで通したら実は210円だった」
ということが起きると思います。表示価格より安く済むので、これに苦情を入れてくる人はまずいないでしょう。
増税時はこれが全て逆転していたので、売価チェックは念には念を、開店して昼が過ぎてもずっと行われてました。一つでもあればお客が会計後に顔を真っ赤にして「値段が違う!!!」と言ってきますからね。

今も昔もそれだけお客は価格にシビアです。買った商品のレシートをじーっと見て確認している姿はよくある光景です。
同様に販売側も「売価登録の漏れや登録ミスに関してはゼロにする」など、その目標は高く設定されていると思います。
要は値下げで苦情は出ないということです。
最後に
うまく説明はできたとは思えませんが、以上のことから値札の変更は減税を留まらせる理由にはなりません。
減税の際も上記のことは実施されていろいろ切り替えが大変でしょう。しかし、店員も含め普段の買い物で安く買えるようになるので時間をかけてもやりきるのではないかと思います。

いきなり「明日から消費税率変更」などということにはならないので、変更される日に合わせて計画的に進めれば値札の変更も業務の一環となると思います。実際に私が店舗にいる期間だけで2回もそれを行ってますからね。
さて、私以外の小売業に従事している方はこの話題をどう見ているのでしょうか??
答えは夏の選挙で出ると思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。
それでは皆さん、今日も1日お疲れさまです。

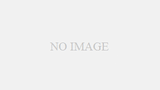
コメント